休息をとる方法
感情が荒れ狂ってしまっている

先週職場で同僚と口論になりました。
当初は継続して取り組んでいる筋トレの効果で、テストステロンが放出されて攻撃的になってしまったと思っていました。
しかし、その後も感情の攻撃性が収まらず苛立つ日々が続いていました。
するとある日、電車の中で2席分を独り占めしている人を見たときに頭を蹴ってやろうかなと思ったのです。
これはまずい・・・。
私はツレに事情を説明して宣言をしたのでした。

当たり前です。
我ながら危ねえやつです。
しかしこのような当然なことを言葉にしてツレに宣言しないといけないぐらいに気が立っていたのです。
そして一つの結論に達しました。
あっ、これはただ疲れているだけだ・・・。
どうやら私は睡眠を含めた休息を軽視していたようです。
最強の成長術

そんなときに手にした一冊の本が、たまたま今の私にぴったりな内容でした。
「最強の成長術」ブラッド・スタルバーグ スティーブ・マグネス著(ダイヤモンド社)
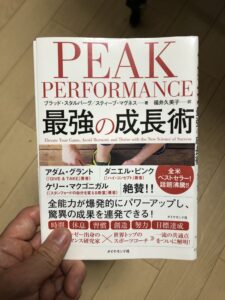
負荷+休息=成長
この図式をこれでもかというほど科学的な根拠を提示しながら説明しているのが本書。
それは勉学の場合、休息をとることで記憶した情報が整理されますし、体の面においても鍛えた後に休息をとることで身体能力が向上するそうです。
仕事終わりにこのブログを書いて、その後に筋トレに行き、帰宅してから夕飯を作ったりして眠るのが1時を過ぎる流れがここ最近続いています。
いっときの早寝早起き生活はどこへやら。
睡眠を蔑ろにした生活に戻っているわけです。
私に必要なのはやはり休息です。


「そうじゃね〜」じゃねーんだよ!!
いかん・・やはり感情が乱れている・・。
睡眠が足りていない

このブログを書いている途中でも何度も意識が飛んでしまい、その都度ブログの作業時間(1時間)を設定したタイマーを止めて、時間を追加し続けてなんとか1時間のノルマを達成することができました。
明らかに睡眠時間が不足しています。
感情に関してはこの1週間は怒り狂ってもいたし、時には異様なぐらいに何かをすることに怯えていた時間もありました。
また「最強の成長術」からこの一文を紹介します。
睡眠は自制心にも影響する
「最強の成長術」ブラッド・スタルバーグ スティーブ・マグネス著(ダイヤモンド社)
休息についてもっと本気になった方が良い

ブログを書かない日や筋トレを控える日を設定する、いわゆる「何もしない日」を作るのが怖いのです。
よって眠いからと言って全てを切り上げて休息することはできず、どれだけ睡魔に襲われていても1時間はブログを書くことを自分に課してしまいます。
冷静に考えると、半分眠りながら書いた文章の出来が良いわけないのです。
それなら見切りをつけてさっさ寝て、早朝に文章を書いた方がクオリティの高いものが(きっと・・)出来上がる気がします。
「最強の成長術」に休息を嫌がる一流のアスリートが納得して休むようになる方法が紹介されていました。
アイアンマンに出場する選手のトレーニング計画を練るときは、「軽めの練習日」だの「休み」だのといった言葉は使わない。その代わり「サポートセッション」と名づけ、計画にたくさん盛り込むのだ。
「最強の成長術」ブラッド・スタルバーグ スティーブ・マグネス著(ダイヤモンド社)
つまり休むこともトレーニングの一環であるという認識を持たせるというわけです。
休息を本気で考えるならスケジュールの中に週に1度でも良いから「休息日」を決めておく必要があると思います。
「休息日」だと漠然としているので、「たっぷり睡眠をとる日」「携帯電話を断つ日」「筋トレの休息日」でも良いと思います。
この「休息日」は家計の収支のことは一切考えずに外でご飯を食べて、ひたすら家でのんびりして、マッサージやサウナに行ったりするのも良いと思います。
週の中日にあたる水曜日あたりを休息日に決めておいた方が定着しやすくなるかもしれません。
携帯電話をいじってしまうと意味がない

「ストレスを操るメンタル強化術」DaiGo著(KADOKAWA)
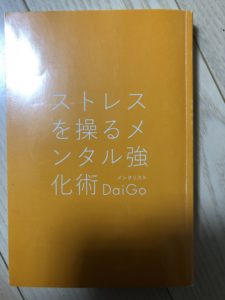
この本の中で気分転換にスマホを見たのでは意味がないということが説かれていました。
集中して作業を行った後に休息をとる場合、携帯電話をいじってしまうとそこでまた一つのことに集中してしまうからです。
効果的な休憩の方法は集中することではなくぼんやりすることで、集中力は一旦気を散らすことで回復するそうです。
確かに携帯電話で遊んだ後は、必ずと言って良いほどちょっとした疲労感に襲われています。
またこのようなことも「最強の成長術」に書かれていました。
人間は起きている間中ずっと何かを一生懸命考えているが、独創的なアイデアの40%は休息中に思い浮かぶのだそうだ
「最強の成長術」ブラッド・スタルバーグ スティーブ・マグネス著(ダイヤモンド社)
しかしこの一文を読んでひたすら休息を取れば良いというわけではありません。
一つのテーマについて集中して考えた末の休息であるということを勘違いしてはならないのです。

