多発性硬化症を完治させたい
腸が原因?

ツレは多発性硬化症という神経の病気にかかっています。
多発性硬化症は視神経の病気からきており、神経細胞の鞘の部分が脱髄といって剥がれてしまい、機能しなくなる病気です。
普段のツレは車いすに乗っており、自分で歩くことができません。
現在は週に4度ほどヘルパーさんが自宅にきて、入浴介助を行っています。
このヘルパーさんがコロナに罹ったら彼女はどうなるのだろう…。
そんなことを考えます。
罹っても今の私は助けに行くことはできません。
そうなると頼みになるのは同居しているお父さんだけ。
そして、もしそのお父さんが罹ってしまったら…?
ツレはそんなことを考えたようで、ヘルパーさんやケアマネジャーさんに相談したそうです。

車いすユーザーは不便な立場です。
そもそもツレが住んでいる地域では、独り暮らしをしている車いすユーザーはおらず、「独り暮らしを考えています!」と言ったら、「前例がないですね…」と返されたようです。
これに関してはツレも私に焚き付けられて言ったところがあったので、特にショックを受けているということもないのですが…。

あっさりそのように言ったツレ。
しかし、これは相当に重たいというか、プレッシャーがかかっているのではないでしょうか。
人の手を借りないと生きていけない心境って、長年一緒にいても私には理解しきれません。
というわけで多発性硬化症は腸の透過性の高さが原因という説があります。
今回は『「腸の力」であなたは変わる』デイビッド・パールマター、クリスティン・ロバーグ著(三笠書房)を取り上げます。
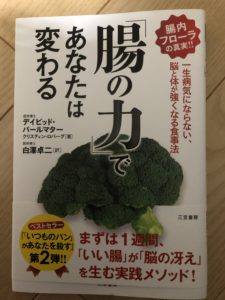
分厚い本。
しかし自己免疫疾患の多発性硬化症のケースがバンバン出てくるので、読まないわけにはいきません。
結局、腸内フローラの乱れがアレルギーからうつ病、自閉症、ADHD、多発性硬化症などの自己免疫疾患の原因となっているということなのですが、これまで読んできた難病改善を謳う本とさほど変わっていないと思います。
「やっぱり腸だな…」と確信することができました。
内容は小難しいです。
ミトコンドリアがエスポージト?云々をコントロールしてる?とかなんとか…。
そんなこと言われてもイメージしづらいのですが、読むうちにワクワクしてきました。
するとツレから電話がかかってきました。




腸の本を読んでるところでツレから電話がかかってきて、病気を治したい宣言。
これはたまたまなのでしょうか?
継続する力が弱いが、意思が強い面もあるので私は期待せずに寄り添いつつ、自分のやりたいことを優先していこうと思っています(ツレに対して我慢するような気持ちを持っていたら関係が崩れると思います)。
きっと「治療しようかな…」と言葉を濁したのは、私が以前「いつまでも治療に付き合っておれん!俺には俺の人生がある!」と怒り交じりに言ったから、それに配慮して濁したのだと思います。
すまん…。
でもその私の考えは間違ってないと思います。
まずは自分の人生を優先した方が良いと思うので・・・。
難病を克服した青年の話

そこで難病を克服した医大生の講演にツレと行ってきました。
今回は我々の意識改善のために、実際に難病を克服した人の話を聞くことが励みになると思ったので、2人で聞きに行くことにしました。
医大生の彼は不治の病気をお医者さんから申告されたとき、自殺かそれとも病気と共生して生きていくか、または克服する道を選ぶかが頭に浮かんだそうです。
そこで彼は克服する道を選んだそうです。
↓講演の会場があった場所

病気というのは体内にさまざまな毒が蓄積されておこるもので、症状というのはその毒を排出するときにおこるものなのだそうです。
病気の克服に大切なのは①食を変える ②体を温める ③笑う ことです。
食生活の改善

医大生の彼は、玄米でおにぎりを作ってお昼に食べる以外にも食生活でさまざまな工夫をしていったそうです。
食事の改善で8割の病気が治るそうです。
何を避けたら良いかを尋ねるとコンビニ弁当などは避けること、また国産小麦以外の小麦を避けること。
そして、乳製品を避けることという返答でした。
しかし、小麦も乳製品なども食材自体が問題なのではなく、そこに含まれる食品添加物やホルモン剤が問題で、結局は人間が加工する行為が害を生んでいるそうです。
体を温める

体を温める点に関しては、体の冷えている箇所が毒が蓄積しているところなのだそうです。
主に肝臓を温めることが有効です。
体の部位を温めるホットパックや湯たんぽが有効かもしれません。
笑うについて

笑うに関しては、笑うことで脳が騙されるそうです。
「この体は幸せなんだ~」と感じると脳内物質のエンドルフィンが放出され、その瞬間は痛みや苦痛は忘れられます。
だから、嘘でも良いから口角をあげましょうとのことでした。
私の感想としては、上っ面の言葉ではなく経験からくる言葉だったので、心に響きましたし言葉が頭に入ってきました。
彼女の感想はというと、いままで西洋医学を目の敵にするような極端な考え方の人が多かったけど、彼はバランスが取れているから良かったとのこと。
彼は医学生ということもあるのですが、医療というのは半分は必要だと考えているスタンスです。
救急医療や精神科の薬の処方はある程度必要。
そして医療を叩くより、それらの中から良いものを選択をして取り入れていくことが必要だと述べていました。
それが私たちからしてみれば新鮮でした。
しかし、そもそも彼は医大生なわけで、医療を信じていないと医学生は志さないと思うので、これは当然の考え方だと思います。
大切なのは情報を得て選択肢を増やすこと

病気が治るという発想が無くて、諦める人が世の中にはたくさんいるはずです・・・・。
一方で難病が克服できると解っている人も世の中にいる・・・。
その違いは知っているか知らないかの違いである・・・・・・。
だから、その知識の差を啓蒙をすることで埋めていけるようになりたいとの趣旨を述べていました。
応援していきたいです。
そのまえにツレ の病気の克服が先ですが…。
