目次
人生で意味のあることをしたい・・。
実は自分が空っぽであるということ

2020年の終わり、実は本棚に置いてある本を全て捨てて、いちからやり直してやろうという衝動が湧き上がっていました。
これまで本に書いてあるノウハウを実践していき、人生をより豊かなものに変えていこうという願望がありました。
そのため本を読んで実践できそうなものをメモにリスト化してその束を常備して、できそうなことを片っ端から実践していたのですが、そのメモも捨てて、本に書いてあることを実践していくという生き方もやめたくなってしまったのです。
このメモの束は私の中では大切なもの・・。

しかしそれが生活に緊張をもたらす窮屈なものということに気づいたのです。
かなり前に「やりたいことリスト」というものを書いたのですが、書いていくと50個を超えるぐらいから手が止まり、捻り出すようにしてやっと80個書くことができました。
人生においてそれほどやりたいことが無いことに、このリストを作成して気付きました。
40すぎた人間ですが、この年齢になってまでやりたいことがそれほど無いわけで、自分の本音の部分を探ってみると人生で意義のあることを為したいという願望も実は世間体をただ意識したものであって、本心ではそれほどやりたいこともない気がしてきました。
空っぽというのは言い過ぎだと思いますが、私の中には本当は何も無いのです。
-
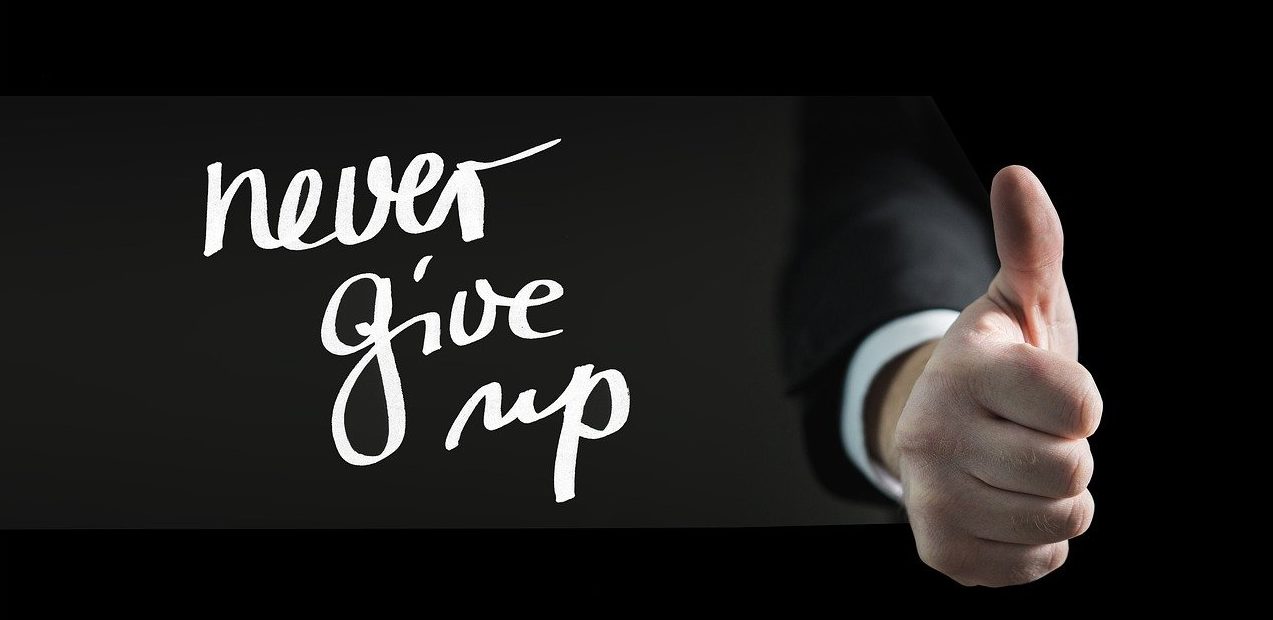
-
「人生でやりたいこと」リストを書く。
目次1 小田桐あさぎさんの著書1.1 「人生でやりたいこと」リスト作り1.2 理想の人生のリスト作りを実践する1.3 50項目過ぎから難産となる1.4 リストに愛着が湧いてくる 小田桐あさぎさんの著書 ...
続きを見る
人生を振り返って、このままだと損をしている気がするから取り返したいだけ・・。

ひきこもり生活。あれはいったい何だったんだ?
デメリットを探し始めたらキリがありません。そこで「ひきこもり」生活のプラスの部分を探してみることにしました。
17歳から23歳まで「ひきこもり生活」を続けてきました。仕事もできずに友達と会うこともなく、病院の先生と家族としか会話がないと自分が誰からも必要とされていないと感じるわけです。生きる意義が感じられないということは辛いものがありました。
26歳でパートの仕事を始めたのですが、その頃も働きながら社会性を取り戻すリハビリは続いていきました。
パートを始める前の「社会的なひきこもり」の時期は家と病院と放送大学との行き来だけでした。時間だけはあって自由に見えますが、怖くて人に会えないし、精神も不安定だったので、できることが限られているわけです。心理的な自由はありませんでした。
一方で働き始めて社会に出ると、辛いことがあっても楽しいこともあるわけです。
「社会的なひきこもり生活」をおくっていた時期は、将来大きく跳ね上がるための助走期間だと思っていました。
だから飛躍しないと割りに合わないわけです。しかし、この年齢になってみると薄々気付くことがあります。
あっ・・こりゃ特に何もねぇ・・・。
不遇の時期を意味のあるものにするために、自分の経験を今ひきこもっている人たちに活かすことはできないか?などと考えたりもしたのですが、人を助けるというのはすごく労力を使うことで、ひきこもりの人は精神が不健康になっていることが多い可能性もあるので、こちらの精神がしっかりと健康でないと巻き込まれてしまう恐れもあると思ったのです。
そこまでして、ひきこもりにこだわりたいか?本当に人助けをしたいのか?という話なのです。
生活が楽しいという感覚が理解できないようだ・・・。

めげずに「ひきこもり」生活のメリットを探してみます。
これまで自覚がなかったのですが、私はどちらかというと「楽しい」や「幸せ」を感じやすいタイプの人間になったようです。
職場の同僚との会話です。
同僚「そんな楽しいことってある?」

同僚「えっ?何があるん?SAVAS?」

同僚「意味がわからん・・生活ってなに?」
自分の生き方は間違っているのではないかと疑問を持つようになり、それから私は幸せになろうと決意しました。
それから「幸福」「感謝」「笑顔」など、自分に足りないと思うワードをAmazonで検索し、出てきた本のなかから数冊購入して読んでみました。
そして実践できそうなものを抜き出してリストを作ったのです。
実践リストを作る習慣はこのときに出来上がったものでした。
自分なりのひきこもりのメリット

およそ9年間「ひきこもり」生活。または「社会的ひきこもり」生活をおくってきました。
フリースペースのスタッフさんから長い人生を考えたらそれは大したロスではないと言われましたが、何もできない時期があまりにも長かったと思うし、多くの機会を失ったと思います。
その失望感と引き換えに得たものが、まともな生活が送れなかった故に幸せを感じるハードルが低くなったというメリットです。
ただ買い物をする。生活を自分の判断でおくる。なんの躊躇もなく出かける。私はそれがとても嬉しくて誇らしいのです。
先ほどの「毎日、楽しい」という感覚を同僚に説明するためには私が以前ひきこもり生活を送っており、遊びにいくこともできなかったし、もちろん仕事もできない。そして人と話をすることもできなかったという状態だったことを説明する必要があるのです。
そんな話を職場の同僚にする必要はありません。
振り返ってみて一番幸せなのはカウンセリングのとき

ちなみに最もこれまでの人生で「ああ・・幸せだな・・」と感じた時はただ自分がこの場にいるだけで良いんだ・・と思ったときでした。
「あなたは特に何かをする必要はありません・・ただここに来れば良いんです・・。」
これ、私が受けていた精神療法の先生が言った言葉です。
何かの宗教ではありません。この意図が分かった瞬間に強烈な幸福感が胸元から込み上げてきて、全身の力が抜けました。
「ああ、俺ってこんなにいつも緊張してたんだな・・。」と思いましたね。このときは・・。
ただここに来れば良い・・って病院の経営的に患者が治療に依存して通い続けることがメリットあるから?とも考えられるのですが、そんなことはあえて無視して、何もない(と思っている)自分がただこの場所にいて良いと思うことが、最も幸福なことだと気づいたことは衝撃でした。
他人が私のことを認める云々ではありません。
他人の評価は不安定なので、それを支えにすることは凄く危険なことです。
そうではなく、自分自身が「このままで良いわけがない・・。」と思っているからガチガチに力が入って窮屈な思いで生きているのです。
根底で「このままで良い・・」と思っていないから幸福感が感じられないのです。
人生の意義よりも私は幸福感を優先させたい。意義のあることに取り組んだとしても自分の心が不幸なままの状態ならそれは望まない人生です。だから、まず自分のことを「これで良い!」と思うことにしました。
「これで良い!」と思うことにする・・のではなく、思うのです。これは今すぐにできることです。脳内言語を意図的に変えていくだけです。
-

-
自己肯定感について考えてみる。
目次1 自己肯定感をあげる理由2 人に頼って生きていく3 頼れないからひきこもる。4 ツレは人を頼らざるおえない5 自分を好きになりたいを読み返す6 自分を好きになるためにできそうなこと7 自分の中の ...
続きを見る