当たり前のことを確実に実践していくということ
人生逃げ切り戦略
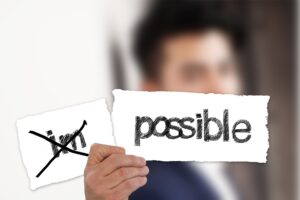
「知っているかいないかで大きな差がつく!人生逃げ切り戦略」やまもとりゅうけん著(KADOKAWA)
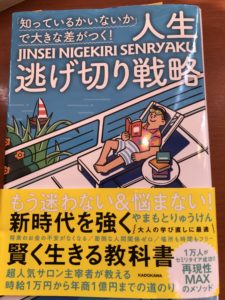
「経済的な不安が限りなくゼロに近づいた状態」そして「面倒な人間関係や誰かに決められた場所・時間に縛られない状態」を著者は逃げ切った状態と定義しています。
そのノウハウを紹介しているのが、この「人生逃げ切り…」なのです。
著者のやまもとさんは1987年生まれ。
このような若い人たちの本を読んでいると、本当に世の中の仕組みが変わっていっているのを感じます。
私の職場にも若者はいますが、同じ若者でも当然ながら身につけている情報の格差は非常に大きいと感じます。
若者でも新しい価値観で仕事をしていく人もいれば、年長者の価値観をモロに受け継ぎそのまま雇われの身で仕事をしていく若い世代の人たちもいるわけです。
これからの時代に合ったスタイルをいち早く取り入れた方が快適な人生が送れる可能性が高くなると思います。
そのためにいかに良質な情報を取り入れて実践していくかが大切です。
ハードルは低いと思う

さて本の中身は実際に買って読んで頂くとして、読んでいて私の印象に残った箇所を取り上げてみたいと思います。
初っ端から話が横道に逸れますが、逃げ切るためには結局個人で稼げるようになることが必須のようで、個人で稼ぐハードルは想像以上に低いということを著者は触れています。
つい私たちは何か新しいことに取り組むときには、知らない故に口癖のように「難しい」「大変」と言ってしまいがちです。
この「人生逃げ切り戦略」の内容の核となる部分とは関係ありませんが、まず「個人で稼ぐハードルは想像以上に低い」というセリフが印象的でした。
このように言えるほど仕組みが理解できているからやまもとさんは逃げ切りに成功できたのではないでしょうか。
頭で理解できていなくても「簡単」「できる」「大丈夫」と口癖になるぐらいに言い続ける必要があると思います。
言葉を変えて前向きなものにしていけば、「大変」「難しい」などの行動を止める考え方をしなくなると思うので、一歩踏み出せるようになると思います。
上位20%に食い込む

さて本題です。
その個人で稼ぐハードルを低くするには、上位20%に食い込む必要があるそうです。
この20%という数字の根拠は不明ですが、何をすれば良いのかというと「当たり前のこと」をやり続けることなのです。
個人で稼ぐためには「起業」や「副業」が必要になってきます。
しかし副業になると「レスポンスが速い」「納期を守る」という「当たり前のこと」ができない人が多いそうです。
「当たり前のこと」でもできない人が多いわけですから、それらができる人に価値が生まれてくるのです。
結果的に「当たり前のこと」ができるようになると、継続的に仕事が受注できるようになるということです。
「当たり前のこと」とは?
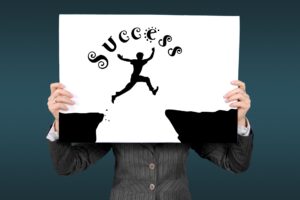
私はいま雇われの身であります。
この「当たり前のこと」は個人で稼ぐだけではなく、現在の雇われの身でも充分に活きてくる知見ではないでしょうか。
当たり前とはなんでしょう・・・。
○ 遅刻しない
○ 無断で休まない
○ 挨拶をする
○ 期限を守る
○ 机の整理整頓
○ 身形を整える
○ 資料を整理して見やすくする
○ 知らないことはすぐに調べる
○ 笑顔で感じよく振る舞う
○ 休養をきちんととって疲れを残さない
「人生逃げ切り戦略」の中に上位20%に食い込む当たり前のことの中身が具体的に言及されているわけではないので、ここは自分で考えていくしかありません。
まず、ざっと考えて思いつくのはこの辺りではないでしょうか。
遅刻とか無断で休まないとか、いちいちあげることか?と思われるかもしれませんが、この箇条書きしたものが全て達成できている人って案外少ない気がします。
これらを全てこなすうちに次のやるべきことがきっと見えてくると思います。
人生改造宣言

「人生改造宣言」ダレン・ミーダナー著(財務経理協会)は非凡な存在にバージョンアップさせる101の方法が紹介されている本です。
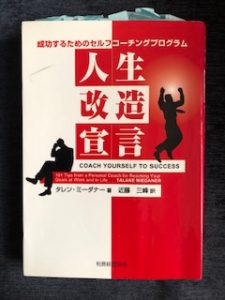
私は1からこの本の内容に取り組んでいるのですが、現在の課題は整理整頓についてです。
これは自宅や職場の整理整頓だけではなく、目的を果たすために取り組むことを整理することなども含まれていると思います。
環境面に関する整理整頓は、物を整理して把握することで探し物をする時間を削減すること。
つまり無駄な作業を省くということです。
これを拡大させて、職場では1人で仕事を行うよりもチームを組んで取り組んだ方が、目的を達成するための労力を減らせると理解する必要があると思います。
私は正規職員です。
臨時職員の方々がいるのですが、特に臨時の男性職員さんと連携をとることが大事であるという当たり前のことを考えます。
仕事の遂行力があまり無い人(自分に自信のない人)は業務を抱え込む傾向があると思います。
抱え込むのは自力で仕事をすることが自分の存在意義に関わってくるからだと思います。
臨時職員さんは控え目な方です。
私はつい仕事を振ったり伝えたりする労力を嫌がってしまい、つい彼を蚊帳の外にしてしまうことがあります。
しかし手間はかかりますが、長い目で見ると出来ることは全て伝えた方が後々私たちも楽になるのです。
そこをもう少し理解しないといけません。
理想なのは同僚の皆さんの得意なことをそれぞれ見極めて、その力を活かせる働きかけが手間を惜しまずにできることだと思います。
仕事上の改善の余地は山のように残っています。

