100のリスト
「100の大好きなことリスト」がついに完成しました!
出来上がったリストを家に持ち帰って早速分類。
私がこの先の人生で取り組みたいことは食や生活、文化、体験、エロ、運動、その他など計9つに分類できるのですが、こうやって一覧にしてみるとこだわりがそれほどないと自認しておきながら意外なことに食が多いのです。
特徴として食の内容は安価なものが多く、やや不健康そうなものを好むのが目につきました。
また運動は少なく、文化的なものが多いのかなと思ったらこれも結果的に少なかった。
海外旅行が好きとか、ブランドものが好きとか、車が好きとかそういうのもなくて、全体的にお金がかからないことで私は満足できるようです。
人生は有限です。この年になって時間ってあまり無いなと思うようになりました。
だからこの「100の大好きなことリスト」に書かれていることを達成するだけで、充分だと思うのですが、私は新しい物事に意識が開けていない人にはなりたくないのです。
これらのリストだけで充分に満たされるけど、新しいことにも取り組んでいきたい。
好きなことは解ったけど、それはいま現在好きなことであって、未知なるものにも関心をもっていこうと思います。だから書き換えを繰り返すことになると思うので、リストが完成することは今後も無いはずです。
-

-
大好きリスト作りに取り組む。
目次1 大・大・大好きリストの作成1.1 100の大好きリストの作り方1.2 手ぶらで生きる1.3 大・大・大好きでないといけない1.4 100の大好きリストの進捗状況 大・大・大好きリストの作成 「 ...
続きを見る
-

-
海で癒されて長期目標を立てる。
目次1 自然に親しんだ後にツレの長期目標を立てる1.1 何かあったら我々は海に行く1.2 長期目標を立ててみる。1.3 人生の100のリスト1.4 やりたい100のリストを作り直す1.5 スペインの巡 ...
続きを見る
やることリスト

紛らわしいのですが、続いては「やることリスト」です。
また「やることリスト」も大半が定着してきたので、新たこれらを追加しようと思います。
本棚を漁って実践可能でやってみたいと感じるものを今回は8つ追加しました。
1、起き抜けに1杯水を飲む。
これは「超効率勉強法」DaiGo著(学研)から取り入れました。
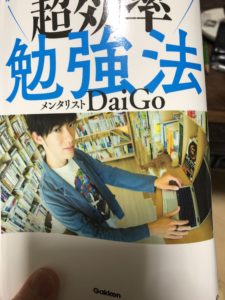
朝イチにプロテインだったものを水に変えました。
お金持ちの習慣を収集した人の話を聞いたことがあって、多くのお金持ちに共通する習慣が、この朝起きて水を1杯飲むでした。
お金持ちになれるから〜ではなく腸を活性化させるための健康に配慮した1杯の水です。
非常に難易度も低くすぐに実践できそうなので、リストに追加。
2、物を弄りながら勉強する。
ミシシッピ大学の実験で、子供たちのワーキングメモリを測るテストを行ったそうです。
足を何度も組み替えたり、机の上をリズミカルに叩いたり、さかんに貧乏ゆすりをしたりと、体を動かす子供ほど成績が上がっていったそうです。
よって集中力を高めて、注意力・文章力・コミュニケーション能力を有意に改善させていこうと思ったら、ボールペンを回してみたり、消しゴムを弄りながら勉強をすると学習効率が上がる可能性があるようです。
本を読むときにリップクリームやノーズミントなどをこねくり回してみようと思います。
小学生の時に授業中にそんなことをしていたら先生から「手悪さすな!!」と怒られていたものですが、どうやらあれにも意味があったようですね。
外食をする機会を増やす

家事に取り組む時間を削減するためには自炊を削って、少しでも外食をする機会を増やす必要があります。
これまでは「お金がもったいない」という意識がありましたが、お金で時間を買っていくのです。
ご飯を作る時間や労力を自分がやりたいことに回していきます。
ということで、外食をするうえで意識するのは食べたことのないものを注文してみるということです。
リストに追加したのは、「頼んだことのないメニューを注文する」です。
馴染みのうどん屋で今日も食事を摂りました。
いつもは温玉ぶっかけというものを注文するのですが、今回は鶏肉のうどんを注文しました。

いつもと違うものを注文する意図は、新たな経験を取り入れて「あっ、意外と美味しい!」と感じることであり、新しいことを体験することに肯定的な意味づけをしていくということです。
しかし、それが完全に裏目。
このうどんの出汁が私の好みではなく、「これなら温玉にしとけば良かった…」と思わせる代物でした。
今回は新しい体験に「快」を感じることはありませんでしたが、行動したという満足感はあります。
だから、これで良いのですができれば美味しいものが食べたいな…。
4.銭湯でぼーっとする。
これは「しないことリスト」pha著(大和書房)を参考にしました。
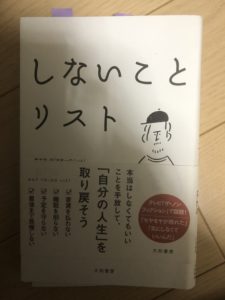
pha(ふぁと読む)さんについては、約束をドタキャンしたり「疲れた…」と口に出す人ということが本を読んでわかりました。
私の周囲にもそのようなタイプの人がいるので、「何てやつだ!」と読みながら一人で憤慨。
私は時間にルーズでもドタキャンはしません。
しかし、このスタンスで生きていて本まで出しているということは多くの人に支持されているということです。
「疲れた」と言ったり、ドタキャンしても人は生きていけるのです。
phaさんの本を読んでいて憤慨したということは「○○じゃないといけない」という考え方が私の中にしっかりとあるということです。
冷静になってみると「生きる型なんて自分が良ければ何でもいいじゃねぇか…」と思うのです。
型を外す柔軟さがあれば、人生がもう少し楽になるかもしれません。型よりも自分の気持ちなのです。
さてphaさんは意識を曖昧にするということを言及していました。
今回は「銭湯でぼーっとする」を追加しましたが、つまりこれは、ぼーっとしやすい環境をつくるということです。
phaさん曰く「何もしないで、ぼーっとする」というのは簡単なようでなかなか難しいものです。
人は刺激を渇望しています。
ぼーっとすることは=退屈ということです。刺激の乏しさに人は耐えられなくなって、すぐに何かしらの刺激を取り入れてしまうのです。
どこかで書いたことかもしれませんが、スペインの巡礼に行った時のこと。
周りの巡礼者たちが使う英語が理解できず、しかも刺激のあまりない山道で疲労困憊状態で私は歩いていました。
余計なことを考えることが一切できない状態でした。そのときに私は不思議な「声」を聞いたのです。
その「声」は私の今後の人生についての質問に、はっきりと全て答えてくれました。私の頭の中から生まれたものとは違う声でした。
その不思議な経験があって以来、理性を省いた「ぼーっとした状態」というのは、きっと何か自分の深いところに繋がる行為なのかもしれないと思ったのです。
本の中でphaさんは、あまり混んでいない電車に乗って適当に町をぶらぶらする。また風呂に浸かって意識を曖昧にする。
それが自分に良いことをしたような気分になれると書いていました。きっと考えない時間を作ることが自分にとって良いことだと体感しているのだと思います。
よって電車に乗って温泉に入りに行くのが最高の組み合わせだと提案していました。
これらを合わせて「ぼーっとする」時間を設けることが大きな気付きになる気がします。
-

-
ぼーっとする時間が何より大切なこと。
目次0.1 宇宙におまかせしたい気分1 仕事が好きになれない2 ぼーっとする。3 ぼーっとする方法を模索する4 ぼーっとしてみて気付いたこと4.1 時間を決めない方がいい。4.2 ぼーっとする時のスタ ...
続きを見る

