あいまいな言葉は責任逃れ
言葉と神経システム

「シリコンバレー式 超ライフハック」デイヴ・アスプリー著(ダイヤモンド社)の中で言葉について言及している章があります。
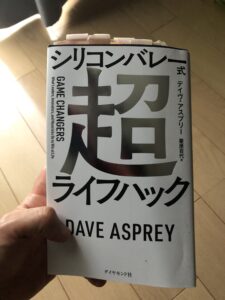
内容としては、言葉は自分自身の神経システムに重要な影響が与えるというものであり、無意識でも自分を弱くする言葉を使っていると、自分が信頼できなくなるうえに、自分で自分の限界を定めてしまうようになるという話です。
以前口ぐせ博士と呼ばれる佐藤富雄さんが、目標をかなえるためには自律神経の働きが重要であると著書の中で述べており、その本を紹介しました。
佐藤富雄さん以外にも言葉に関しては多くの著者が言及していることなので、私もそれにならって極力後ろ向きな言葉などを避けるようにしているところでした。
今回、言葉の問題に関しては、「あいまい語」を回避することを著者はお勧めしています。
「あいまい語」とは?
詳細を紹介していきます。
-

-
目標を叶えるには設定とワクワクすることと実行すること。
目次1 佐藤富雄さんの本1.1 佐藤富雄さんの11個のプラクティス1.2 目的達成のプロセス1.3 網目様神経系によって情報を拾い集める1.4 実現したい欲望について1.5 ドーパミンの働きについて1 ...
続きを見る
あいまい語とは

「あいまい語」とは悪い意味で自己制限をかける言葉であり、責任回避につながる弱い言葉にあたります。
「あいまい」ではなく明快な言葉は、明快な思考と実行につながるという考え方です。
というわけで「あいまい語」と呼ばれる言葉を本の中でいくつか紹介されていたので紹介していきたいと思います。
できない
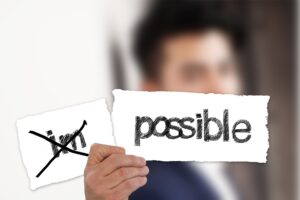
今回は「あいまい語」をすべて紹介するのではなく、日常生活もしくは仕事の場面で共感できる「あいまい語」を2つ挙げていきたいと思います。
まずひとつ目ができないという言葉。
「できない」のだから、何かをやり遂げる方法は絶対に存在しないということを意味する。それはあなたのパワーを奪い、画期的な考えを押しつぶしてしまう。
「シリコンバレー式 超ライフハック」デイヴ・アスプリー著(ダイヤモンド社)
職場でもこの言葉をよく使う同僚がいますし、私は極力この「できない」とか「無理」って言葉を使わないように意識しているつもりなのですが、言葉に出さなくても頭の中でそのように思っていることが結構ある言葉です。
私には将来の目標があるのですが、頭の中ではそれは将来叶えたいことであって「今の私にはできない・・」と思っています。
そのマインドがあるから、いつまで経っても状況が進展しないままにずるずると年を重ねているのです。
今の私にはできそうにないから、怖くて現状を変えたくない。
でもいずれはできるようになりたい・・・と思っており、変わる覚悟が私の中でまだ足りていないのです。
「できない」と言うときの意味は4つあると本の中で説明されていました。
1、だれかに助けてもらえたらできる。 2、手段がない。 3、方法がわからない。 4、やりたくない。
私の実感としては、職場で「できない」と言っている同僚は4の「(面倒だから)やりたくない」という意味が言語下に含まれていると感じます。
ちなみに著者のデイヴ・アスプリー氏は「できない」という言葉は嘘だと理解するようにプログラムされているようです。
だから他人から「できない」と言われたときには、それは嘘だと解釈するそうです。
その発想で著者はトラブルを切り抜けているわけなのですが、そのときの顚末は著書を読んでいただくとして、「できない」は嘘だ。と考える習慣が身についていれば、脳が別の方法で問題解決をするようになっていくそうです。
やってみる
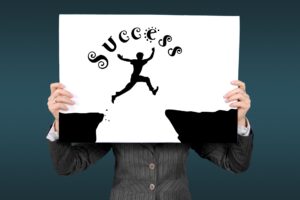
これは私もよく使っている自覚のある言葉です。
ヘラヘラ笑いながら同僚に対して言うことがあるのです。

私の職場でもよくあることなのですが、提案したときに誰がそれを実行するのか?その辺が曖昧になっていることがあります。
積極的に仕事をこなす人は、手をあげてしまうとオーバーワークに陥ってしまうので様子を見る。
仕事をあまりしたくない人は面倒なので手を挙げずに様子を見る。
だから誰も「私がやります」言い切らずに責任が曖昧になってしまうのです。
ダイエットをやってみようとか、本を読んでみようなどと自分に言い聞かせるとき、あなたは無意識のうちに失敗を計算に入れている。きっと実行せずに終わるだろう。
「シリコンバレー式 超ライフハック」デイヴ・アスプリー著(ダイヤモンド社)
「やってみる」は一見すると、行動につながる言葉なので私からしてみたら積極的な言葉だと思っていたのですが、その言葉には失敗に対する保険も含まれているそうです。
「やってみる」がダメなら、なんと言えば良いのでしょう。
やはり「やります」と言い切ることがベストなのだと思います。
ただし自分にとって精神的なストレスが大きくなりすぎる事柄まで無理やり「できる」とか「やります」と言い切らない方が良い場合もあると思います。
以前私は職場の組合活動を断れずに、いやいや参加していたことがありました。
そのときは本当に参加することが不快で、毎回行くたびに後悔と苛立ちを感じていました。
「できる」「やります」「できない」は嘘と口に出すことを意識していく必要もありますが、何に対して「できる」「やります」と言うかその見極めもすごく重要なのです。
